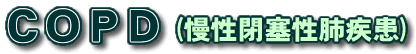
| 咳や痰、息切れが続くのは… |
| 咳や痰、あるいは息切れは、よくある症状です。それだけに”変だな??”と思いつつも、そのままにしてしまいがちなものです。でも、それが長引くなら注意が必要です。気管支や肺、あるいは心臓になにか異常があるかもしれません。 長引く咳・痰・息切れの原因となる「慢性気管支炎」と「肺気腫」について説明します。 この2つは医学的に「慢性閉塞性肺疾患」と呼ばれています。気管支が閉塞(狭まる)ような症状が、長く続く病気という意味です。適切に治療しないでいると、呼吸機能が少しずつ悪化し、心臓病なども起こり、日常生活から徐々に快適さが奪われていきます。慢性気管支炎と肺気腫は、併発することもよくあります。慢性気管支炎や肺気腫と言われたら、それがどんな病気なのか、正しく理解することが大切です。 |
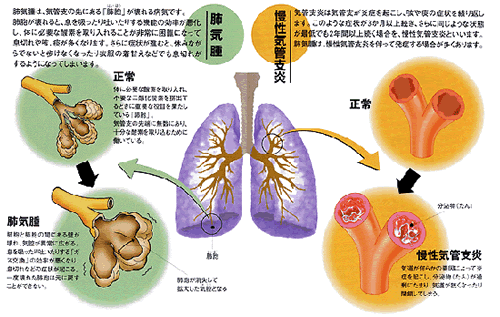
マルホ株式会社『増えているCOPD』参照
| ・COPDにかかる患者さんの数は、1996年では、男性13万人、女性では9万人で、そのうち男性78%、女性70%が65歳以上の患者さんです。 |
| ・厚生省の人口動態統計(1996)によると、COPDによる死亡者は、約1万2千人です。また、65歳以上の慢性気管支炎および肺気腫による死亡率は約1万人となっています。 |
| ・最近の調査では、COPDの患者数は潜在患者を含めると約530万人と言われています。わが国の急速な人口の高齢化と、先進国としては高い男性の喫煙率から、COPDの患者数と高齢者を主体とした死亡数はますます増加していくものと考えられます。 |
|
||||
| 他にも、喘息症状、乳幼児の肺炎、成長期の低栄養状態、大気汚染などもCOPDのリスクが高くなります。 |
| ・COPDは発症すると、元の状態に戻ることがほとんどない病気です。 |
| ですから、治療は病気の進行をできる限り防ぐこと、症状をやわらげること、そして生活の質を向上させることが基本になります。 喫煙者は、最大のリスクである喫煙をやめることが重要です。喫煙が治療の大前提です。 そして、治療薬や包括的な呼吸リハビリテーション(呼吸法・ストレッチング)を覚えておくことも大切です。 |
 ☆治療に使う薬 ☆治療に使う薬・気管支を拡げるために(気管支拡張薬) 【β2刺激薬(貼付・吸入) 抗コリン薬 テオフィリン剤】 ・炎症を抑えるために(抗炎症薬) 【吸入ステロイド薬】 ・感染による悪化をくいとめるために 【抗生物質】 ・痰を出す、あるいは溶かすために 【去痰薬・喀痰溶解薬】 |
| ☆酸素療法 ・COPDが進行し、血中の酸素が著しく不足すると、呼吸不全になります。高度の呼吸不全には、長期的酸素吸入を行います。現在は酸素濃縮器の普及によって家庭での酸素吸入が容易になりました(在宅酸素療法)。軽量のボンベを使えば外出も可能です。 |
| ☆腹式呼吸は肺の負担を軽くしてくれます。 ・鼻から息を吸いお腹をふくらませ、吐くときは口をすぼめてゆっくりと。 きちんとできているかどうか、胸とお腹に手をあてて動きを確認しながら呼吸します。 階段を上がるときも、ゆっくりと「2回息を吸って、3回吐く」腹式呼吸でリズムをもって上がります。 |
| ☆ストレッチングで運動不足や無理な呼吸でこり固まった筋肉を伸ばす。 (伸ばすときは息を吐きながら行いましょう。) |
| ☆筋肉トレーニングで歩行や呼吸の際に必要な筋肉を鍛える。 |
| 1番注意が必要なのは、症状が急激に悪化する急性増悪期です。多くの場合、冬場の風邪やインフルエンザなどの感染症が原因です。呼吸困難や血液中の酸素量の低下などが起きて、入院が必要になることもあります。 予防法として、インフルエンザシーズン前の予防接種、こまめにうがいをする、室内の加湿・保湿などがあげられます。暖房器具の使用は特に乾燥しますので、洗面器に水を張ったり加湿器を用いてください。そして、もし自覚症状がひどくなったり、発熱や頭痛が起きたときは、早めに診察を受けて下さい。 |
| COPDが急に悪くなると、それが原因で死にいたることさえあります。 |
 次のような症状が起こったら、軽く考えずにすぐ病院に行きましょう。 次のような症状が起こったら、軽く考えずにすぐ病院に行きましょう。・息切れがひどくなったとき(動作時も含む) ・咳が長く続いたり、ひどくなったとき ・心臓がどきどきするとき ・熱が出たとき ・足が浮腫んだり、体重が増えたとき ・痰の量が増えたとき・痰の色が変わったとき(黄色・緑色・血が混じるなど) ・肌が紫色になったとき |
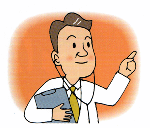
◎とにかく「体の調子が普段と違う」と感じたら、早めに対応しましょう。
さらに迷わず病院に連絡を入れることが大切です。