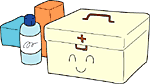| 片頭痛は「慢性頭痛」のひとつです。 |
多くの人が日常生活において「頭痛」を体験しますが、「頭痛」と一言でいっても原因や症状によっていくつかの種類があります。頭痛は痛みの起こり方によって、大きく「日常的に起こる頭痛」、「慢性頭痛」、「脳の病気に伴う頭痛」に分けられ、片頭痛は「慢性頭痛」のひとつです。頭痛の中にはくも膜下出血や脳出血、髄膜炎、脳腫瘍といった脳の病気によって引き起こされる「危険な頭痛」があり、これらを鑑別することが重要になります。何の前ぶれもなく突然あらわれる激しい頭痛には特に注意します。
| 日常的に起こる頭痛 |
かぜ、二日酔いなどが原因の頭痛です。・・・本人も頭痛の原因がわかりやすく、原因が解消されれば症状は治まります。 |
| 慢性頭痛 |
原因がはっきりしないまま、繰り返し起こる頭痛です。・・・いわゆる「頭痛持ち」の頭痛で、その原因や痛みによって「片頭痛」、「緊張型頭痛」、「群発頭痛」の3つに分けられます。突然強い頭痛に見舞われ、動くと楽になったり、悪化したりする頭痛が繰り返し起こり、しかも次第にひどくなっていったりします。 |
| 脳の病気に伴う頭痛 |
くも膜下出血や脳腫瘍などの脳の病気が原因の頭痛です。・・・何の前ぶれもなく激しい痛みが現れる事が多く、生命に危険が及ぶケースもあるので注意が必要です。このような頭痛はMRI(磁気共鳴画像)やCTスキャン(コンピュータ断層撮影法)といった検査で診断できます。 |
|
|
| 片頭痛ではこのような症状が起こります。 |
片頭痛が始まると、あまりの痛みに動くこともできず、仕事や勉強などが手につかなくなってしまいます。頭痛に伴って吐き気がしたり、光や音に過敏になったり、体を動かすと痛みがひどくなったりするため、部屋を暗くして洗面器を抱えて寝込んでしまうこともあります。片頭痛の痛み自体は、休息や睡眠により和らぎます。また、発作が治まると次の発作が起こるまで、全く症状がみられなくなります。
●片頭痛の症状
| 第1相:予兆 |
うつ状態、情緒不安定、気分がすぐれない、傾眠、あくびの頻発、空腹感、口渇、特定の食物(特に甘いもの)の渇望 |
| 第2相:前兆 |
視覚障害(閃輝暗点)半盲)、片麻痺、しびれ、失語 |
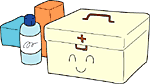 |
| 第3相:頭痛 |
随伴症状(悪心、嘔吐、光過敏、音過敏) |
| 第4相:頭痛消失後 |
筋肉の疲労感と痛みを伴う疲労困憊感および離脱感 |
| 第5相:回復期 |
|
●症状の特徴
- ズキンズキンと脈打つような強い痛み(拍動性頭痛)が4〜72時間続く
- このような痛みが月に1〜2回、多い人では週に1〜2回発作的に起こる
- 頭の片側のこめかみから目にかけての辺りが痛むことが多い(頭の両側や後頭部が痛むケースも見られる)
- 頭痛に伴って、吐き気がしたり、実際に吐いたりする
- 光や音に過敏になる
- 体を動かすと痛みがひどくなる
- 頭痛が起こる「前兆」として、閃輝暗点や半盲、片麻酔などの症状が出る場合がある
|
|
| 片頭痛はこのような誘因で起こります |
片頭痛の発作は何らかの誘因によって起こります。日常生活でのストレス、騒音やまぶしい光などの環境、また家族に頭痛持ちの人がいるとなりやすいなど、誘因には様々なものがあります。
●片頭痛の誘因
| 1.過労や睡眠不足、精神的ストレス |
|
ハードな仕事をやり終えたとき、大きな悩みから開放された時など、それまで抑えていたストレスから一気に開放されて緊張が緩んだときにも頭痛はおこりやすくなります。これは、ストレスのかかっている最中には緊張によって収縮していた血管が、リラックスすることによって拡がるための考えられます。実際、平日は何でもないのに、せっかくの休日に朝から片頭痛に悩まされるという人は少なくありません。 |
| 2.特定の食べ物 |
|
人によっては、アルコール(特に赤ワイン)、チーズ、チョコレート、カフェイン(過剰摂取)、柑橘類あるいは食品の防腐剤として使われている亜硝酸塩、グルタミン酸などの添加物によっても片頭痛が誘発されるといわれています。しかし、これらの食べ物が直接頭痛に影響しているかどうかは疑問視され、食べた時の状況に関係がある場合も考えられます。 |
| 3.空腹 |
|
ダイエット中であったり、朝食を食べないで学校や会社へ行くと、頭痛が起こることがあります。 |
| 4.人ごみや騒音、まぶしい光 |
|
デパートなど人の集まる場所に出かけると、頭痛が起こる場合があります。この場合、人込み、騒音、蛍光灯などの明るい光、ストレスあるいは香水の匂いなどによって頭痛が誘発されていると考えられます。また、旅行に行くと頭痛が起こる場合もあります。旅行には、車酔い、早起き(寝不足)、不規則な食事、疲労、ホテルの部屋の乾燥、ストレス、ストレスからの解放など、頭痛に関連する多くの要因が絡んでいます。 |
| 5.睡眠 |
|
寝過ぎ、寝不足も片頭痛の誘因となります。 |
| 6.家族歴 |
|
家族や親族の中にも同じような頭痛持ちの人がいることが多く、その点から遺伝的体質との関係も考えられます。特に母親が片頭痛の場合、娘が片頭痛になる確率が高いことが知られています。 |
| 7.気候の変化 |
|
低気圧が近づくと頭痛が起こりやすいことが知られています。また、寒さによって頭痛が誘発される場合があります。頭痛は冷房している室内で、冷気が直接頭に当たる場合などによく起こるので、頭や首にスカーフを巻くなどして冷気を防ぎます。 |
|
|
| どの診療科を受診したらよいのですか? |
まず、「神経内科」を受診してみましょう。
「慢性頭痛」の場合、医療機関のどの診療科を受診したらよいのか、悩むところです。例えば、風邪をひいて頭が痛いなら一般内科ですが、原因か思い当たらない頭痛が続くときには、まず脳や神経系のトラブルの診断・治療を専門としている診療科である「神経内科」を受診してみます。慢性頭痛は、脳の周辺の血管や神経、筋肉などに痛みのある原因があると考えられるので、神経内科を受診するのが最も適しています。
神経内科では、問診や体温・脈拍・血圧などの計測といった一般的な診察をした後、「神経学的検査」を行います。座ったまま、あるいは仰向けになった状態で、首や手足に麻痺や筋肉の萎縮などがないかどうかを調べたり、歩行困難や姿勢の異常といった症状の有無を確認します。
慢性頭痛については、診断をくだしたり治療方針を決める上で、問診は大変参考になりますので、実際は次のようなことをメモして行きましょう。
- いつから起こったのか
- 発作的かダラダラ痛みが続くのか
- 頭痛の持続時間
- 痛む方
- 痛む場所
- 付随する症状(吐き気、前兆症状)
|